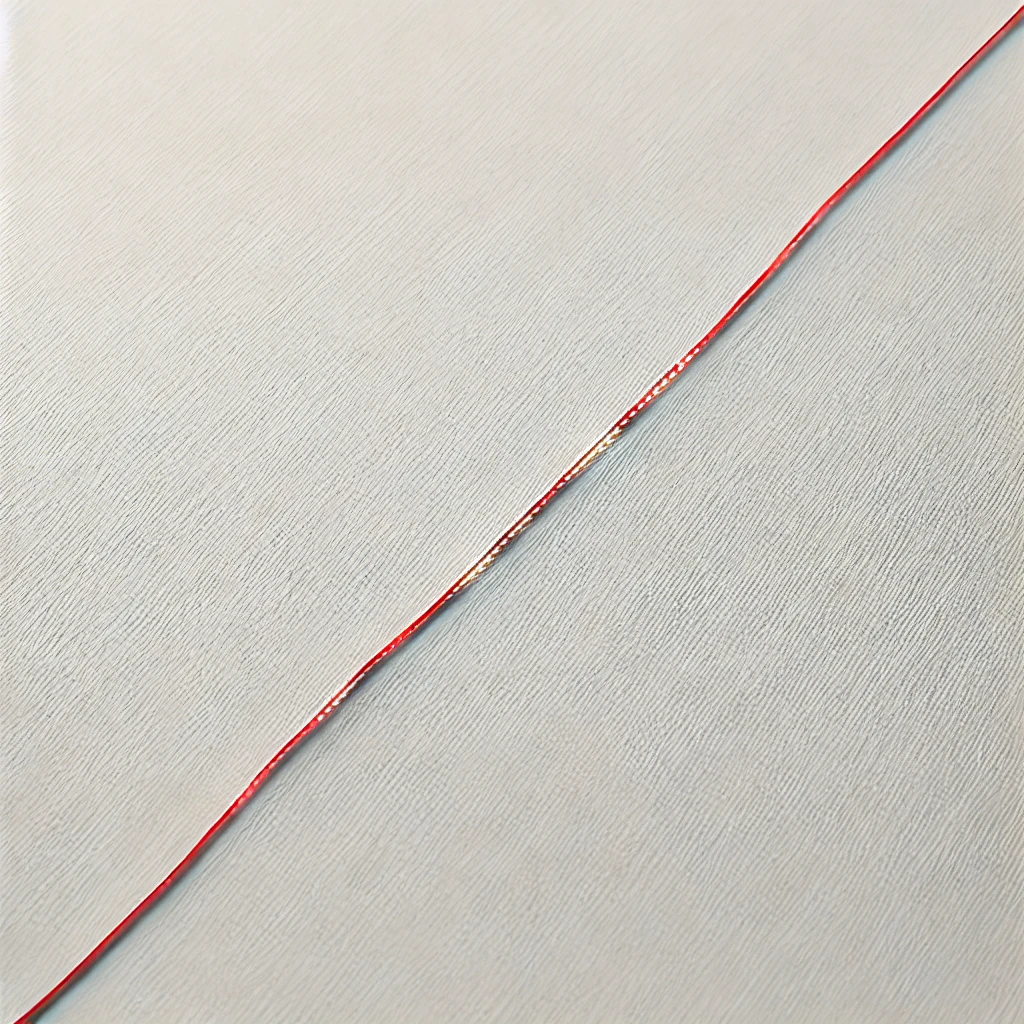田中康弘は、明朗とした、けれども快活かと聞かれるとそうではない、そんな青年だった。大学3年の学祭で話しかけられたのが彼を知ったきっかけだが、いつから親しくなったのかはあまり覚えていない。サークルや趣味が同じというわけではなかったし、彼の友人とは到底仲良くなれると思えなかった。彼もそれを分かっていたから、お互い暇な日に会う程度だった。
そう聞くと、表面上のつきあいみたく聞こえるかもしれないが、彼と過ごす時間はどこか特別だった。傍から見ると、似ているようには見えない僕らだったが、同じ目をしていたことを今でも思い出す。翳りの中に、一筋の光を見出そうとするような、そんな目を。
親密さとはいつだって、どこか似ているからこそ生じるもの。共通項がなければ引き合わないし、全て同じなら磁石みたいに反発する。からこそ、田中とは上手くいっていた。
2人でキャンプをしに熊本の方へ行ったことがある。お互い田舎育ちということもあって、魚を捕まえたり、買った肉を焼いたりした。夜明けまで話していたことは今でもいい思い出だ。冷えた空気の中、僕らは火を囲んで座り込んでいた。火の揺らぎが彼の顔を照らしたり陰らせたりしながら、彼はふと空を見上げた。
「星が全部、同じ明るさだったらどうだろうな。」
「どういうこと?」と笑いながら聞くと、彼は真剣な表情で続けた。
「強い光に負けて見えない星があるだろ。そういうの、なんだかもったいないなって。」
意味がわかるような、わからないような。そんな抽象的な話を彼は好んだ。言葉を交わすたびに、彼の中には手の届かない何かがある気がして、それが不思議と心地よかった。
あの日、僕らはどんな話をしたのだろう。大学のこと、将来のこと、夢のような話―たぶん、そんなものだ。夜が明ける頃には、僕らは無言で空を見上げていた。空が白み、川の水が朝日に照らされて輝いていた光景を、今でもはっきりと覚えている。
けれど、その後、僕らが何度会ったのかはもう思い出せない。卒業後、連絡が少しずつ途絶え、彼の近況を聞くこともなくなった。ただ、ふとした瞬間に彼の言葉が頭をよぎることがあった。
―星が全部、同じ明るさだったらどうだろうな。
翌朝、窓を開けると冷たい空気が一気に流れ込んできた。庭先には、解けきらない雪がまだ残り、木々の枝が陽の光に淡く輝いている。支度を整え、「近くの機織り工場を見てみたいのですが」と宿の老婦人に尋ねると、にっこりと笑顔を浮かべて地図を広げてくれた。
「この道を少し行ったところに、小さな工場がありますから。村の人が手仕事で織っているところね。案内してもらえると思うわよ。」
宿を出ると、空気はまだ冷たかったが、陽射しに少しずつ春の匂いが混ざっている気がした。老婦人に教えてもらった通り、小さな工場はすぐに見つかった。瓦屋根の低い建物で、外には染めた糸が乾かされている。風が吹くたび、それらが音もなく揺れた。
中に入ると、機織りの音が静かに響いていた。木の織機が規則正しく動き、そのリズムが、何か大切なものをゆっくりと紡いでいるようだった。ひとりの職人がこちらを一瞥する。一作業終えると、ぶっきらぼうに話しかけられた。
「いらっしゃい。観光客の方?」
「はい、少し見学させていただきたくて。」
職人の手元を見ると、一本一本の糸が繊細に重なり合い、布が形を成していた。その模様には、微妙な濃淡があった。
「この織物、糸を染める色の違いで模様を出すんですね。」
「そうさ。染め上がった糸は一見すると単純だが、それぞれが違う色合いを持っている。それを組み合わせて、布に模様を浮かび上がらせるんだよ。」
「全部、同じ色じゃだめなんですか?」
思わず口をついたその言葉に、自分でも少し驚いた。職人は少し笑いながら首を振った。
「同じ色じゃ、何も生まれない。濃い糸も、薄い糸も、それぞれがそこにあるから模様になるんだ。」
「織物って、すごいですね。」
そう呟くと、職人は朗らかに笑い、再び織機に手をかけた。木枠の揺れる音が、静かな工場に心地よく響く。その音を聞きながら、僕はハンカチを軽く握った。
(続く)