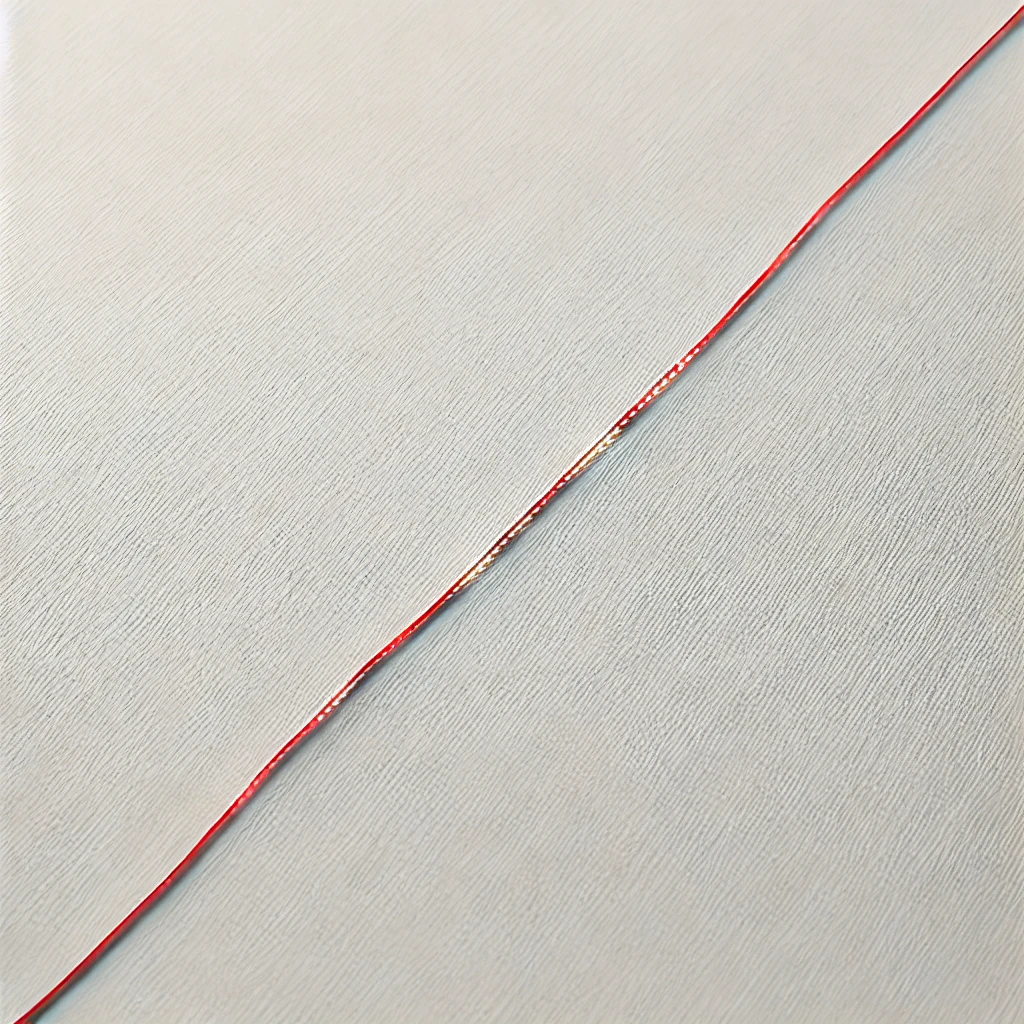四角くくり抜かれた景色は、まるで切り貼りされた絵のようで、どこか嘘っぽい。流れる雲も、遠ざかる街並みも、ただの装飾とさえ思えてくる。東京を発ち、向かった先は山形県最上地域の山中にある「ツイナ村」。明治時代、日本の紡績業を支えたこの村は、当時の産業遺産と豊かな自然を活かし、今では観光に力を入れているという。
改札を出ると、構内には村の歴史が記されていた。「明治20年代、ツイナ村は日本有数の紡績地として知られていた。村中に響く織機の音が人々の暮らしを支え、織物は全国へと出荷されていったという。特に紅花は、鮮やかな赤色を生む染料として、村の重要な産業だった。」
手描きの紅花や織機のイラストが壁を彩っている。地元の小学生が描いたのだろうか。溌剌としたもの、丁寧なもの、剛直なもの。整然さに囚われ、いつしか零れ落ちていた記憶を、穏やかに呼び起こしたクレヨンの香り。所々に貼られた白黒写真は、かつてのツイナ村の活気を静かに物語っている。
ふと出口近く、大きな地図が目に留まった。遠目にはよくある観光案内図に見えたが、近づくと息を呑んだ。観光名所や山々の起伏、川の流れ―そのすべてが、糸と染料の微妙な濃淡で表現されていたのだ。
地図を織り上げたのは村の染織職人たち。山の高さや川の流れを繊細に再現するため、何度も糸の配置や染色の濃淡を試したという。説明書きの一文が、糸の一筋一筋に込められた時間の重みを伝えている。その精緻な仕事ぶりに村人達の誇りが見えて取れ、思わずポケットの中のハンカチを探した。
駅前の小さな案内板を頼りに、宿へと歩みを進める。ぽつぽつと現れる古びた家々の縁側には、干された藁や紅花らしき束がぶら下がっていた。頬をなでる風は引き締まった感じをもっていて、足元の砂利は乾いた音を立てながら靴底を押し返してくる。その気配が静寂の中へと溶け込むたび、時間そのものが逆行していくような、不思議な感覚にとらわれた。
やがて見えてきたのは木造の小さな宿。「ツイナ荘」と書かれた看板が掲げられ、屋根の先からは雪解け水が細く滴っている。玄関を開けると、木の温かみを感じさせる柔らかな空気と、ほうじ茶の香りが迎えてくれた。
「いらっしゃいませ。」
奥から現れたのは、小柄な老婦人だった。しわの刻まれた手で、湯気の立つ湯飲みを差し出してくれる。「遠いところをようこそ。ここはまだ雪が残っていてね、驚かれたでしょう?」
湯飲みを両手で包み込むと、冷えた指先がじんわりと温まる。
「ゆっくりなさってくださいね。」
老婦人の優しい声が、木の壁に吸い込まれるように消えていく。軒先の雪は、太陽に溶かされながらも、どこかしぶとくその存在を主張している。帳場の椅子に腰かけて、庭前の鹿威しが時を刻む中、先週送られてきた手紙を読み返す。記されていたのは友人の訃報だった。
(続く)